文:たなかよしゆき 絵:のさかゆうさく 出版:福音館書店
奥が深い、泥団子作り。
まん丸ピカピカの泥団子を作るのは、中々大変。
そんな、泥団子の作り方と、泥団子を使った遊びを描いた絵本です。
あらすじ
子どもたちが、泥団子作りを始めました。
まずは、地面に穴を掘り、そこに水を入れてかき混ぜます。
泥でクッキーを作ったり、スープを作って遊びます。
次はいよいよお団子作り。
そのまま丸めたり、中に石を入れて丸めたり・・・。
丸めたら、乾いた砂をかけ、まぶしながら握ります。
ひびが入っても大丈夫。
水につければ、やり直しできます。
もう一度握って、そうっと撫でて・・・。
泥団子の完成です。
それぞれ、大きさも硬さも形も違う泥団子。
泥団子が完成したら、高いところから落として、硬さ比べをしてみます。
硬さ比べをした後は、次のゲームが始まります。
次はどんな遊びでしょう?
『どろだんご』の素敵なところ
- 泥の作り方から描かれる泥団子作り
- 泥団子を使った遊び
- 実際の泥遊びに繋がっていく
泥の作り方から描かれる泥団子作り
この絵本の素敵なところは、泥団子作りに必要なことが、1から全部描かれていることです。
穴を掘り、そこに水を入れ泥を作る。
この泥作りから描かれているので、泥団子作りが初めての子も、どうしたらいいかがわかります。
泥団子の作り方も、わかりやすく順を追って描かれているので、困ることがありません。
絵本を見て、自分で1から泥団子作りの実験をできるのです。
やってみようと思った時に、自分で調べて、自分でやってみることができるのがこの絵本の素敵なところです。
泥団子を使った遊び
また、泥団子を作って終わりではないところも、この絵本の素敵なところ。
作った泥団子での遊びも描かれているのです。
高いところから落とす硬さ比べでは、たくさんの泥団子を落とすところが描かれます。
粉々になる子、ひびが入る子、割れない子・・・。
それぞれの泥団子で、結果が違います。
それを見ていると、作り方で硬さや割れやすさが違うことが感じられます。
そして、その違いが、色々な泥団子を作ってみようという好奇心にも繋がるのです。
作り方だけなら、「きれいに丸くしてみよう」というところで、終わりになっていたと思います。
そこを、遊びまで描くことで、泥団子作りをより楽しく、より興味深いものにしているのが、この絵本のとても素敵なところです。
実際の泥遊びに繋がっていく
さて、泥団子の作り方もわかり、遊び方もわかったら、実際にやりたくなるのが道理というもの。
子どもたちも、
「泥団子作りに行きたーい!」
「いいな~、楽しそう・・・」
と、作りたくてうずうずしてきます。
このやりたい気持ちを生み出してくれるのも、この絵本の素敵なところ。
そして、やりに行った時に、どうやって作るか思い出しながら、自分で試行錯誤していけます。
見ることでやり方がわかり、それが実際の遊びに繋がり、うまくいかなかったらまた絵本に戻ってくる。
「今度は石を入れてみよう」
「すっごい小さいの作ってみようかな」
「卵の形にしてみよう」
など、楽しい循環が生まれていくのです。
二言まとめ
泥の作り方から、泥団子を作った後の遊びまで、一冊で泥団子のことがまるっとわかる。
見たら、泥団子を作りに外に遊びに行きたくなる、泥団子作りの教科書絵本です。
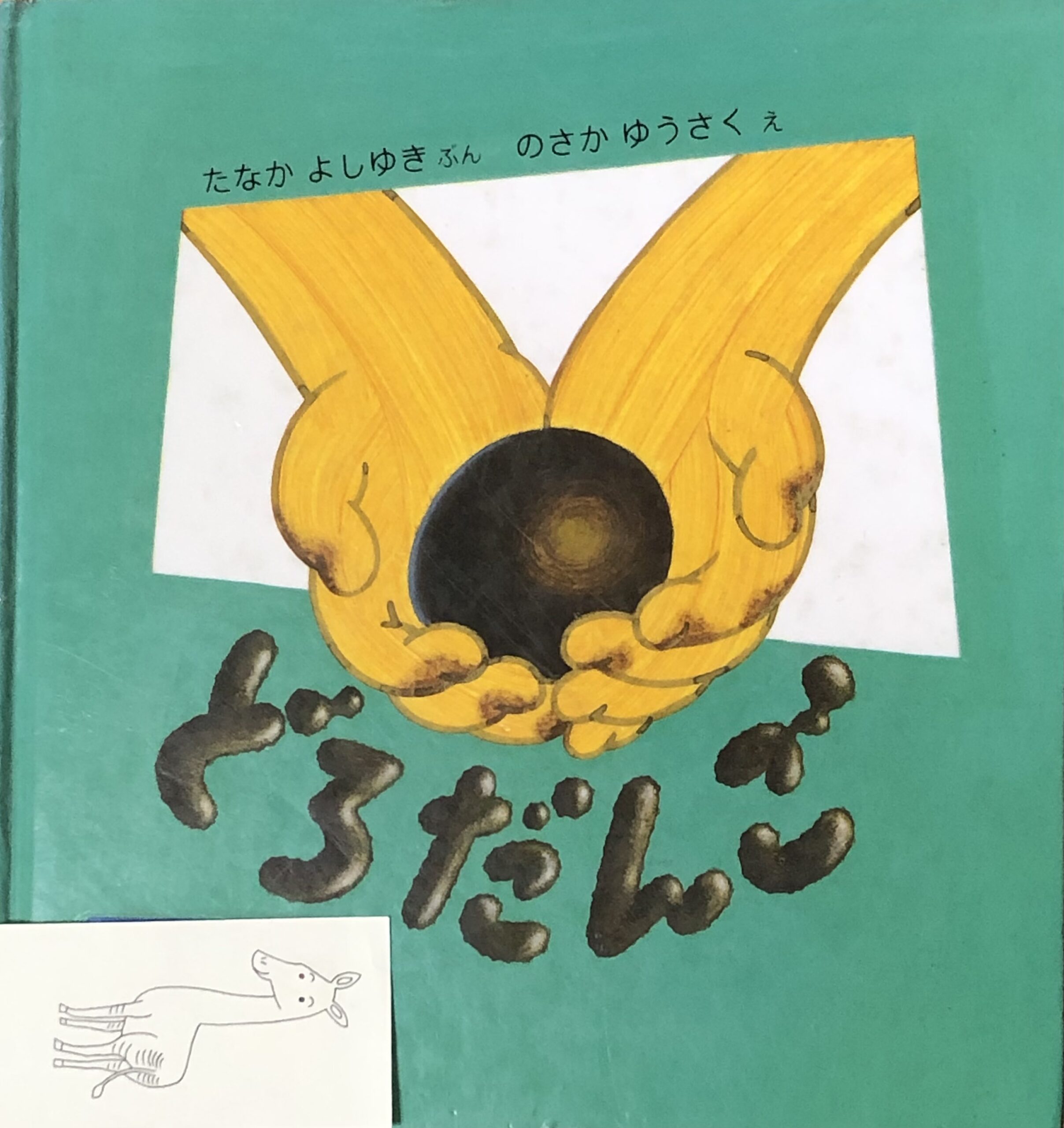


コメント