お元気様です!
登る保育士ホイクライマーです。
みなさんは「保育心理学」という名前を聞いたことがありますか?
きっと、発達心理学や児童心理学という言葉を知っている人は多いと思います。
それらと関連はありつつも、また違った心理学の分野です。
ぼくも、ある本を読んで初めて知った言葉でした。
けれど、学んでみると、保育士にとっても、保護者などの保育者にとっても、非常に重要なものであることがわかりました。
保育心理学とは簡単に言うと、「日々の保育の現場で起きている実践から、子どもや保育者の心理を探っていこう」というものです。
- 食事を食べさせられるのを嫌がる子どもと保育者の対応
- 保育者に注目してほしくて問題行動をする子
- 大人と一緒にパズルをし、段々と自分で出来るようになっていく子
そんな普段の保育所や家庭でよくある保育の場面から、「どんな心理が働き、どんな発達が促されていくのか?」。
そんなことを考えていきます。
詳しくは、この後、『保育心理学の基底』(著:石黒広昭)という本を元に紹介していきますので、気になった方はぜひ見ていってください。
ではいってみましょう!
保育心理学ってどんな心理学?
まずは、保育心理学について詳しく見ていきましょう。
保育心理学とは、日常の保育実践から、そこに働いている子どもや、保育者の心理を読み解こうというものです。
- 食事でのやりとり
- 絵本の読み聞かせ
- 友だちとのけんかと仲立ち
そんな保育の中で日々起こる出来事から、そこに関わる人たちの心理を探っていくのです。
子どもや保育者の心理には、実に様々なことが影響しています。
子どもと保育者のその時だけの関わりだけでなく、日々の関わり方、前後の出来事、保育環境、他児との関係性などなど、非常に多くのことが関わり合って、その保育場面での心理へと行きついているのです。
例えば、噛みつきが多いということで、保育心理学の視点を持って保育場面を見てみたとしましょう。
すると、その子の発達段階として噛みつきが多いのではなく、パーソナルスペースが狭いという保育室の環境が原因でイライラしているとわかるかもしれませんし、保育者が声をかけすぎてストレスになっているのが原因だとわかるかもしれません。
さらに、その保育環境を作らざるを得ないのは、建物の構造や保育者の不足によるものだと、より外側の環境に実は原因があるかもしれません。
同時に、噛みつきが多いことによる保育者のストレスがピリピリした空気を生み、それに反応して噛みつきが起こるという悪循環に陥っている可能性もあります。
このように、当事者や、子ども個人の発達だけでなく、その事例の中のすべての要素や、日々の連続した時間軸の中で、「どんな心理が生まれているのか?」「どうしてその心理が生まれたのか?」を考えていくのが保育心理学の特徴です。
この部分が発達心理学や児童心理学などの、主に個人の発達や心理に主眼を置いた心理学と大きく異なるところです。
3歳児健診などで、発達について指摘される時などは、主に発達心理学の目線でなされますが、それは日常生活とは切り離された姿を見られていると言い換えることもできます。
もちろん、個人発達の視点も必要ですが、それだけでは見えてこない部分もあるはずです。
それを見るのが保育心理学と言えるでしょう。
また、これらは保育所での出来事に限りません。
家庭や学童での子どもとのやりとりなど、すべての保育を対象としています。
保育心理学で大切なこと
それではここから、保育心理学の具体的な内容を見ていきましょう。
保育心理学の視点で、保育実践を見る時には、いくつか大切な考え方があります。
ここではそれらを順番にお伝えしていきたいと思います。
研究的視点と3つの「みる」
まず大切なことは、保育実践を研究者として「みる」ということです。
研究者として「みる」というのは、その保育実践が「どんな目的を持っていて、その中でどんな原因で、どんな心理や発達に繋がり、どうしたらよりよくなるか?」ということを言語化・理論化するということです。
そのためには、3つの「みる」が必要だと言います。
1、保育を「観る」
これは保育を、一歩引いて俯瞰的に観るということです。
先にあげた噛みつきの例であれば、パーソナルスペースが確保できていないなど、子ども本人以外の問題に気付いたりします。
保育を観る時に重要なのは、その子どもや周辺だけでなく、より広い視野でクラス全体や園全体を観るということ。
そうすることで、客観的に保育を観て、新たな保育課題に気付くきっかけになるのです。
2,子どもを「診る」
これは子どもの現状を診断し、予測を立てるという見方です。
その子の振る舞いや、発達段階、他者とのかかわり方を診るなど、発達心理学で個人を診る視点に近いものと言えるでしょう。
この時大切なのは、色々な人との関わりや場面の中で「診る」こと。
そして、長期的な時間軸の中で「診る」ことです。
そうすることで、ある一場面だけで、診断してしまうことを防ぎ、多面的・複眼的な視点でその子を「診て」、保育計画を立てることに繋がります。
3、子どもを「看る」
これは保育の実践者として、関わるための見方です。
目の前の子どもたちを「看ながら」、どのように関わるかを考えていく。
「こうした方が遊びが広がりそうだ」「こうした方が伝わりやすいかもしれない」など・・・。
まさに保育者がいつもしている見方でしょう。
この3つの「みる」は、切り離すことができません。
目の前の子どもを「看て」関わり、その実践を「観て」保育課題を探し、その中での子どもを「診て」、そして実践者としての「看る」に帰ってきて、よりよい保育を展開する。
このサイクルを作ることで、保育実践の解像度があがり、研究的視点を持って保育実践をみることができるようになるのです。
相互行為論的視座
保育心理学では、環境との関わりの中で、その行為が生まれるという相互行為論的な見方をします。
子どもたちは、色々な人や環境との関わりの中で、甘えや挑戦、問題行動など、色々な行為をしながら発達していくという考え方です。
当たり前のように思われますが、心理学では多くの場合、なにかの行為があった場合、その原因をその子の発達や能力、家庭環境など、その子個人に焦点を当てて見ています。
これを個体能力主義と言います。
知識や能力は、その子の中に貯めこまれ、使われるのもだという見方です。
この考え方は、その子が関わるものから切り離した考え方と言えるでしょう。
けれど、実際には個体能力主義的見方では、読み解けないこともあります。
それは、知識や能力を社会的な場の中で使ったり習得した時、その能力を獲得した以上の変化が起きることがあるからです。
例えば、ボールを蹴ることができるようになった時。
この時「ボールを蹴ることができるようになった」という能力的変化が起きるだけではありません。
自信に繋がったり、蹴ることができるようになったことで、いつもサッカーをしているグループに「入れて」と言えるように気持ちの変化があるなど、別の変化も引き起こします。
もし、サッカーのグループに入れてもらえたら、「ボールを蹴ることができるようになった」という能力的変化だけでなく、サッカーグループの一員になったという社会的変化も起こっているのです。
このように、相互行為論的な見方により、子どもや保育の見方は大きく変わります。
保育心理学では、その子を個別にどうにかしようとするのではなく、環境へ働きかけることで、その行為をよりよいものへと変えていこうとするのです。
保育心理学の対象は、保育に関わるものすべて
ここまで見てきて「保育心理学の対象って子どもだけじゃないの?」と感じた方も多いのではないでしょうか?
その通りです。
保育心理学が研究の対象とするものは、保育に関わるもの全てなのです。
ここがこれまでの子どもだけを対象とした、発達心理学や児童心理学などと大きく違うところです。
子どもはもちろんとして、保育者も当然対象となります。
これは、保育者の悩みを解決したり、成長を促すことも研究対象に含まれているということです。
子どもや保育園環境との関わりの中で保育者を見ることで、個人だけを見た時には気付かなかった課題や、本人とは別のところに原因があることを見つけることができます。
保育者にとって、これほど学びになり、助けになることはないでしょう。
また、保育室や園全体の環境も対象になります。
さらには、園を取り巻く地域の環境も対象です。
地域の治安や、図書館などの社会資源の有無、子どもの大きな声に寛容か?など、保育に影響を及ぼすものも多いでしょう。
同時に、補助金の制度などにより、保育者の処遇や、保育所運営の質、家庭での子育てのしやすさにも影響があるかもしれません。
もっと広げると、国の政策なども対象になります。
こうして、現場の保育実践から、その実践の意義を探り、課題点や問題点があれば、その原因がどこにあるのかを「みて」探っていく。
そして、その原因がどんな環境に起因するか?
それをどうすればいいか?
これらの保育に関わるものすべてを対象にし、包括的に環境を見て、その環境を変化させることで、保育をよりよいものにしていくのが、保育心理学の考え方なのです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は保育心理学という、保育の見方・研究の仕方についてお話してきました。
なにか課題や問題があった時に、子どもや保育者個人の能力の問題にされがちですが、保育心理学の視点で見てみると、そこには非常に複雑な心理が働いていることがわかります。
その心理は、言葉がけや目線、行動など、様々なことに影響し、保育実践を作っていきます。
けれど、日々の保育をする中では、いっぱいいっぱいになり、中々俯瞰的に見ることは難しいでしょう。
その中で全体を俯瞰して見ることができる、保育心理学の考え方や、研究手法はとても有用なものではないでしょうか?
本書の中では、様々な研究手法を用いて実際に保育場面を見た具体例や、より詳しい理論がたくさん載っているので、興味を持った方には、ぜひ読んでみて欲しい一冊となっています。
個人的には、保育心理学の考え方が広がることで、子ども個人の発達や能力に保育が引っ張られてしまうことや、保育者個人の能力が責められ自信をなくしてしまうことへの特効薬だと感じています。
ぜひ、保育者だけではなく、管理職の方や、子どもに関わる全ての方に保育心理学が広がればいいなと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました!


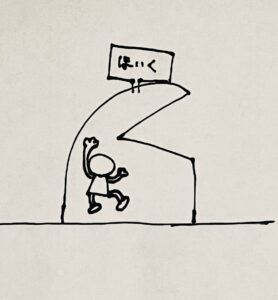
コメント